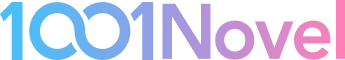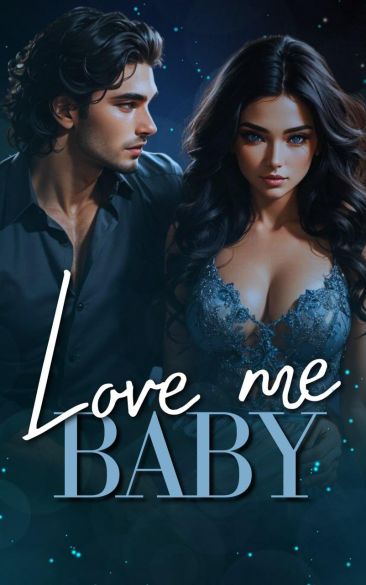



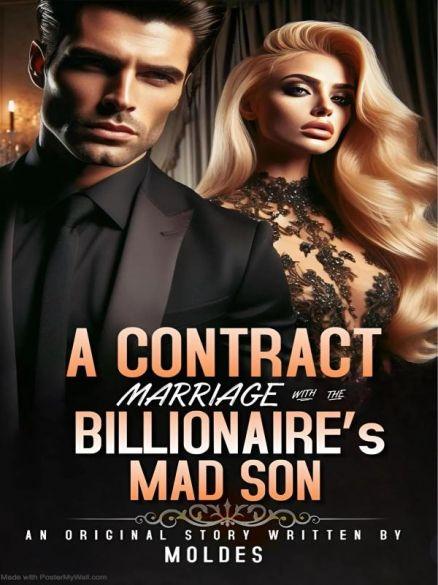

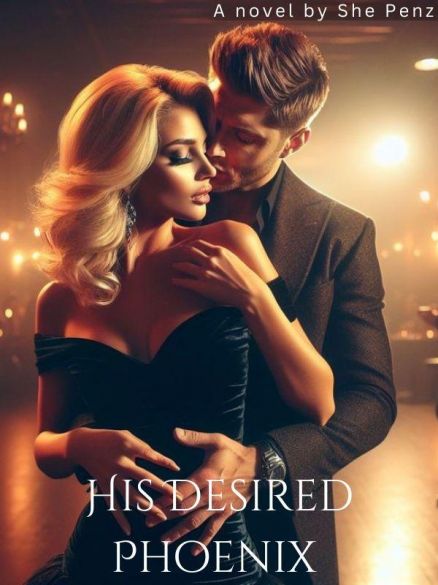
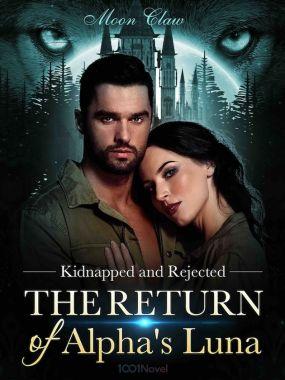




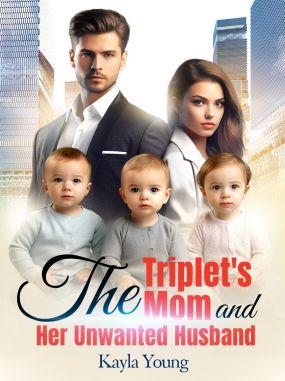







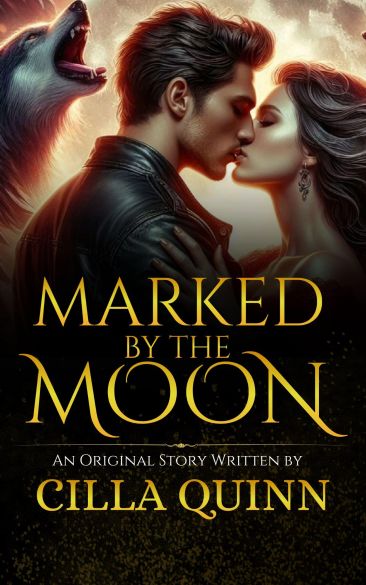
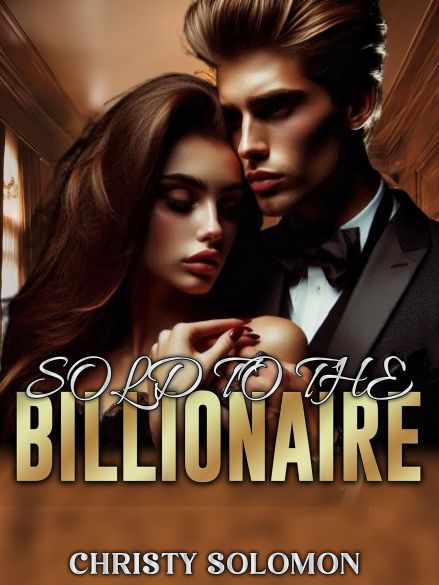





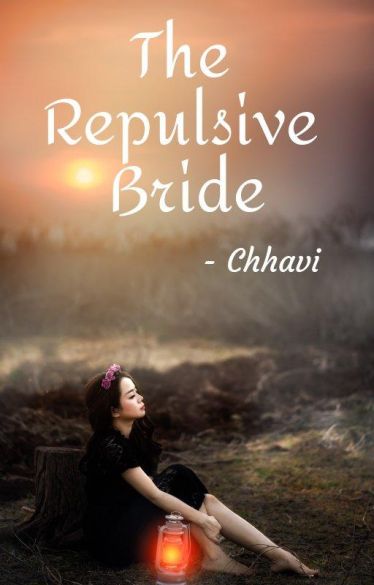


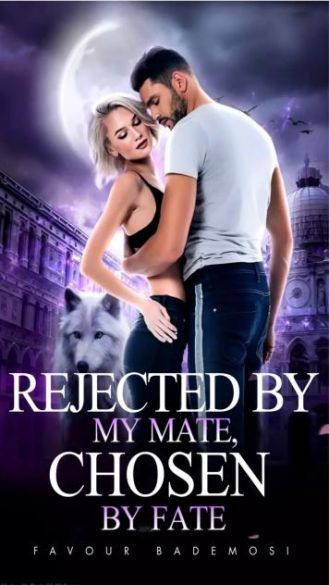
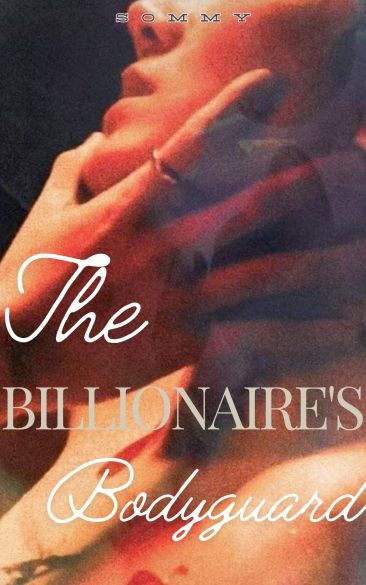



むせ返るような酒の匂いと、安っぽい芳香剤の香りが混じり合う化粧室で、私は便器に突っ伏していた。胃の中身をすべて吐き出しても、不快感は一向に消えない。今夜の投資家は特にたちが悪く、次から次へと高価な酒を無理強いしてきた。
「……っ、うぇ……」
私はなんとみっともない。情けない。これが、小さなアパレル会社「リ・クチュール」の社長、橘莉子の姿だなんて誰が信じるだろう。
三年前、神代黎(かみしろれい)に捨てられた時、私は泣きじゃくることしかできない無力な小娘だった。けれど今は違う。金のためなら、プライドなんていくらでも捨ててみせる。会社を守るためなら、なんだってする。
鏡に映る自分の顔は、青白く、化粧も崩れかけていた。その時だった。背後に、見覚えのある長身の影が立ったのは。
「……橘?」
凍りつくような低い声。振り返るまでもない。この声の主を、私が忘れるはずがない。
神代黎。
三年前と変わらない、冷たく射抜くような瞳。高級そうなスーツを完璧に着こなし、まるで別世界の住人のように、彼はそこに立っていた。彼が醸し出す圧倒的な存在感は、この薄汚れた化粧室には不釣り合いだった。
「……神代、さん」
かろうじて絞り出した声は、震えていた。彼がここにいるなんて。なぜ?
黎は私を一瞥すると、フンと鼻を鳴らした。その瞳には、かつて私に向けていた熱はなく、ただ憐憫と軽蔑が浮かんでいるように見えた。
「相変わらずだな、お前は。そんなところで何をしている?」
「少し、気分が悪くて」
言い訳にもならない言葉だった。彼は、私の今の状況などお見通しだろう。
そうだ、三年前の別れ際、彼は言った。「お前みたいな女に、俺の隣は務まらない」と。彼の家柄、彼の社会的地位。それらに釣り合う女ではなかったのだ、私は。あの時の絶望と屈辱は、今も鮮明に思い出せる。そして、金があれば、もしかしたら何かが違ったのかもしれないという、醜い後悔も。
「さっさと戻れ。相手を待たせているんだろう」
「……はい」
彼の言葉は常に命令形だ。それに逆らう術を、今の私は持っていない。
よろめきながら個室を出ると、先ほどの投資家がちょうど化粧室に入ってくるところだった。私と黎の姿を見て、その顔色が一瞬で変わる。
「こ、これは神代社長!このような場所でお会いできるとは光栄です!」
さっきまでの尊大な態度はどこへやら、投資家は黎に対して卑屈なまでに腰を低くしている。これが、資本を持つ者と持たざる者の差。嫌というほど見せつけられる現実だった。
「橘さん、大丈夫ですか?顔色が優れないようですが」
投資家は猫なで声で私に尋ねる。その変わり身の早さに、吐き気がこみ上げてくる。
「いえ、少し飲みすぎてしまったようで。お見苦しいところをお見せして申し訳ありません。お詫びに、もう三杯、頂戴いたしますわ」
私は作り笑顔を浮かべ、そう言った。場を丸く収めるためには、これくらい何でもない。
黎は黙ってその様子を見ていたが、やがて口を開いた。
「橘と言ったか。お前の会社、資金繰りに困っているそうだな」
心臓が跳ねた。なぜ彼がそれを?
「……どこでお聞きになったのですか」
「この業界は狭いんでね。いくら必要なんだ?」
彼の言葉は単刀直入だった。値踏みするような視線が、私を射抜く。
「……五千万、です」
それは、今の私の会社にとって、喉から手が出るほど欲しい金額だった。
黎は少し考える素振りを見せた後、ポケットからスマートフォンを取り出し、どこかへ短い指示を出した。そして、あっけらかんと言った。
「わかった。投資しよう。契約書は後日送らせる」
「え……?」
あまりに突然の申し出に、私は言葉を失った。こんな簡単に?あの神代黎が?
「ただし、条件がある」
彼の目が、再び冷たく光る。
「LINE、交換しろ。それから……この会食が終わったら、俺のところへ来い」
彼の言葉の意味を理解するのに、時間はかからなかった。これは、そういうことだ。金と引き換えに、私を再び彼のものにしようとしている。
唇を噛み締めた。屈辱で全身が震える。けれど、会社のためだ。ここで彼の申し出を断れば、リ・クチュールは潰れる。それだけは、絶対に避けなければならない。
「……わかりました」
私は、声が震えないように、必死に平静を装った。
会食は何事もなかったかのように終わり、私は黎に指定されたホテルのスイートルームの前に立っていた。ドアを開ける指が、震える。これから起こることを考えると、逃げ出したかった。しかし、もう後戻りはできない。
部屋に入ると、黎はバスローブ姿でソファに座り、グラスを傾けていた。
「遅かったな」
「申し訳ありません」
彼の前に立つと、まるで蛇に睨まれた蛙のようだった。
「服を脱げ」
命令だった。私は黙って、着ていた安物のワンピースのファスナーに手をかけた。布が床に落ちる音だけが、やけに大きく響いた。
彼の視線が、私の裸の体をゆっくりと舐め上げる。羞恥と屈辱で顔が熱くなるのがわかった。
「……相変わらず、いい体だな」
彼はそう言うと、私を手招きした。ベッドの上で、私はただ彼のなすがままになった。かつて愛し合った男との行為は、今はただの取引でしかなかった。彼の荒々しい愛撫に耐えながら、私は天井のシミを数えていた。涙が溢れそうになるのを、必死で堪える。これは仕事だ。そう自分に言い聞かせながら。
事が終わり、黎は満足そうにタバコに火をつけた。紫煙が部屋に立ち込める。
「やっぱりな」
彼は、吐き出した煙の向こうで、私を見て言った。
「お前は結局、俺の元に戻ってくる。俺にはわかっていたよ」
その得意げな声が、私の心の奥深くに突き刺さった。そうだ、私は結局、この男の手のひらで踊らされているだけなのだ。三年前も、そして今も。
私は何も答えず、ただシーツを握りしめた。これが、私と彼の「復縁」の始まりだった。金で買われた、かりそめの関係。
そして、ここから先の私の人生は、さらに大きく歪んでいくことになる。彼の一言が、それを予感させていた。