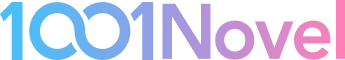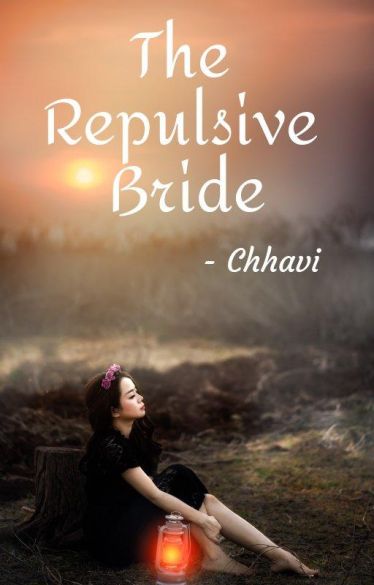





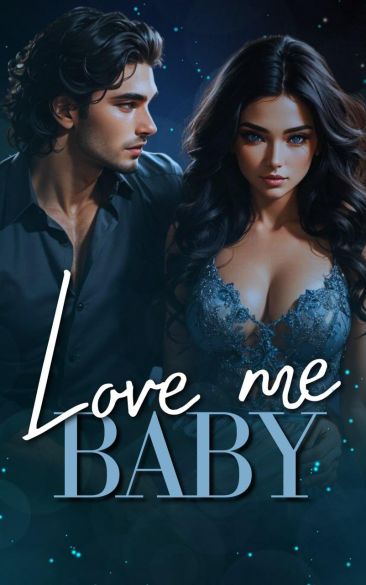
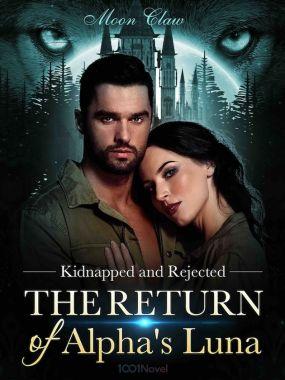







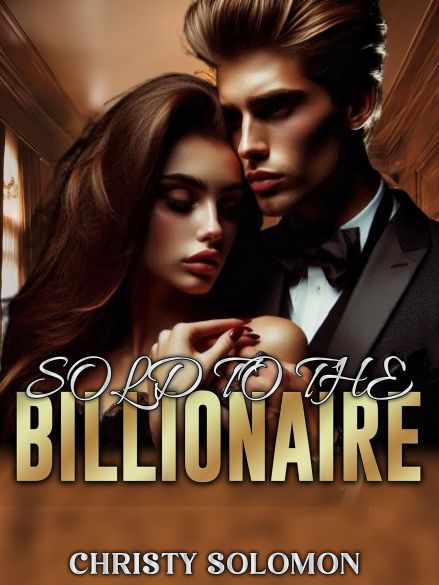



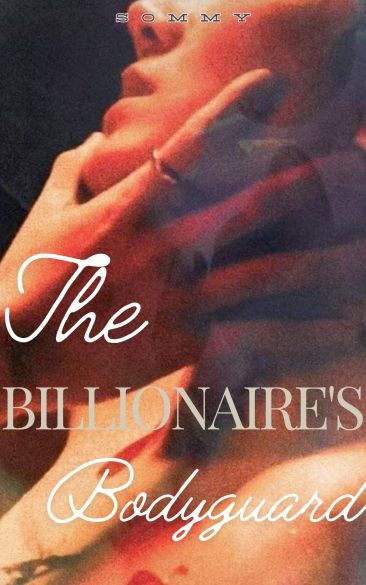



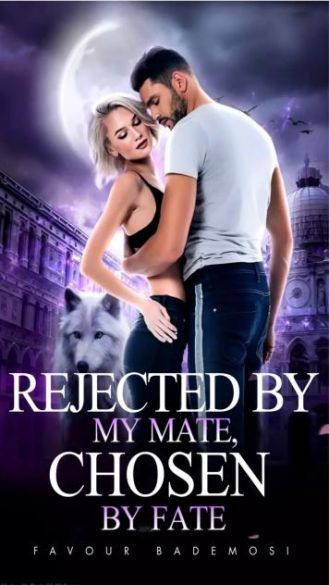
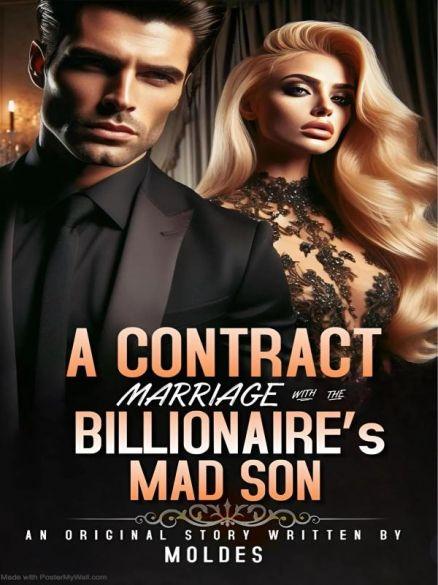





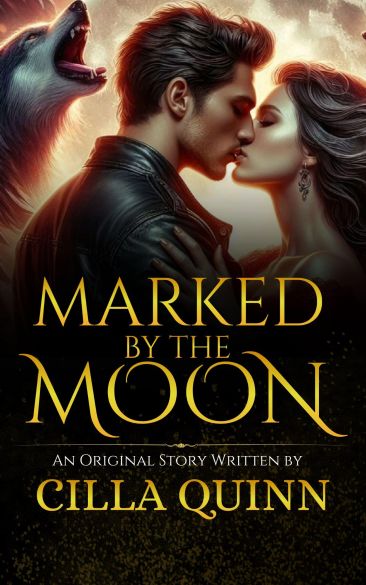

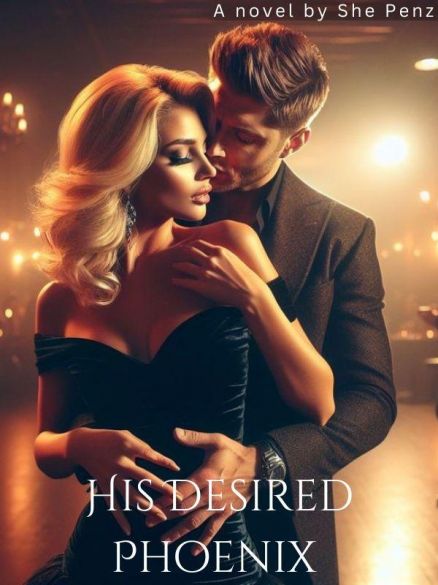
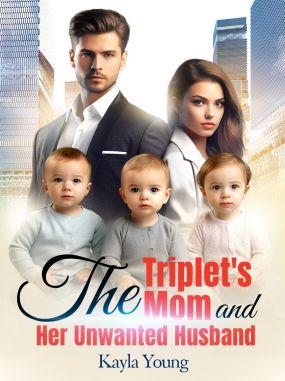
私、藤咲 結菜には、双子の妹がいる。杏奈(あんな)という名の、それはそれは可愛らしい妹が。
私たち姉妹の関係は、まあ、普通とでも言っておこうか。特別仲が良いわけでもなく、かといって憎み合っているわけでもない。ただ、生まれた瞬間から、私たちの間には見えない壁があった。
私は、物心ついた頃には両親に疎まれ、まるで存在しないかのように扱われた。理由は知らない。ただ、そこに「私」がいたから、というだけのことなのかもしれない。一方、妹の杏奈は、両親の愛情を一身に受け、蝶よ花よと育てられた。欲しいものは何でも与えられ、常に笑顔の中心にいた。私とは、まるで違う世界に生きているようだった。
そんな杏奈に、ある日、とんでもない縁談が舞い込んだ。相手は、一条グループの御曹司、一条響。眉目秀麗、頭脳明晰、そして何より、この国の経済界を裏で牛耳るとまで噂される一条家の次当主になる。誰もが羨む、まさに玉の輿だった。
両親は狂喜乱舞し、杏奈も満更ではない様子だった。だが、結婚式を間近に控えたある日、事件は起きた。
「杏奈が……杏奈が、いなくなったんです!」
母が、電話口でヒステリックに叫んでいた。受話器越しに聞こえる父の怒鳴り声。どうやら、杏奈は書き置き一つ残して、姿をくらましたらしい。
「はあ、そうですか」
私は、どこか他人事のように相槌を打った。正直、胸の奥が少しだけ、スカッとするのを感じていた。ざまあみろ、と。いつも自分勝手な妹と、それに振り回される両親。いい気味だ。
電話の向こうで、母がさらに泣きわめいている。「一条家に、なんて説明したら……! きょう様に、顔向けできないわ!」
自業自得だろう。私は冷めた気持ちでそう思った。
それから数日後、憔悴しきった父が、私の前に現れた。やつれた顔には、深い隈が刻まれている。
「結菜……お前に、頼みがある」
父が、私の名前を呼ぶなんて、何年ぶりだろうか。いつもは「おい」とか「お前」なのに。ろくな頼みではないことは、すぐに察しがついた。
「何ですか」私は努めて無表情に答える。
父は、ゴクリと唾を飲み込み、意を決したように口を開いた。「杏奈の代わりに……響様のところへ、嫁いでくれ」
「……は?」
何を言っているんだ、この男は。冗談だとしても、笑えない。
「お前たちは双子だ。顔も声もそっくりじゃないか。髪型と化粧を少し変えれば、誰も気づきはしない」父は必死の形相で私に迫る。「この通りだ! 一条家との縁談が破談にでもなったら、うちはもう……!」
「お断りします」私は即答した。「なぜ私が、そんな馬鹿げたことのために人生を犠牲にしなきゃいけないんですか? 杏奈の尻拭いは、ご自分でどうぞ」
「結菜、頼む! このままでは、私たち一家は路頭に迷うことになるんだぞ!」母までが、いつの間にかそばに来て泣き落としにかかろうとする。
「自業自得でしょう」私は冷たく言い放った。彼らがどうなろうと、私の知ったことではない。散々私をないがしろにしてきたくせに、困った時だけ頼ってくるなんて、虫が良すぎる。
父は、私の冷たい態度に一瞬言葉を失ったようだったが、すぐに何かを思いついたように、ニヤリと卑しい笑みを浮かべた。
「……五百万円。いや、税金を引いて、手取りで五百万円を渡そう。それでどうだ?」
五百万円。その金額は、今の私にとって、無視できない額だった。養母の病状は芳しくなく、治療にはまだまだお金がかかる。あんな両親でも、金蔓として利用できるなら……。
私の心が揺らいだのを、父は見逃さなかった。
「考えてみろ、結菜。ただ結婚するだけで、大金が手に入るんだ。響様は素晴らしいお方だ。お前だって、悪いようにはされないはずだ」
「……」
「どうだ? やるのか、やらないのか」父は、まるで悪魔の囁きのように、私の耳元で繰り返す。
私は、唇を噛み締めた。心の奥底で、何かがプツリと切れる音がした。怒り、諦め、そしてほんの少しの打算。
「……わかりました。その話、受けます」
私の返事を聞いた父は、顔をくしゃくしゃにして喜んだ。「本当か! さすが私の娘だ!」
私の娘、ね。都合のいい時だけ、そう呼ぶ。私は心の中で嘲笑った。
こうして、私は妹杏奈の身代わりとして、一条響のもとへ嫁ぐことになったのだ。
この選択が、私をどんな運命へと導くのか、その時の私には知る由もなかった。ただ、手に入るはずの五百万円のことだけを考えていた。