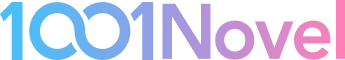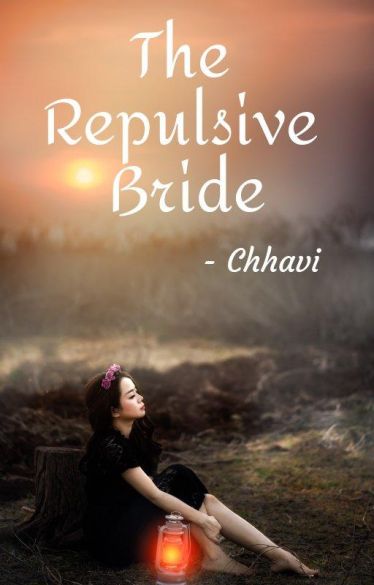
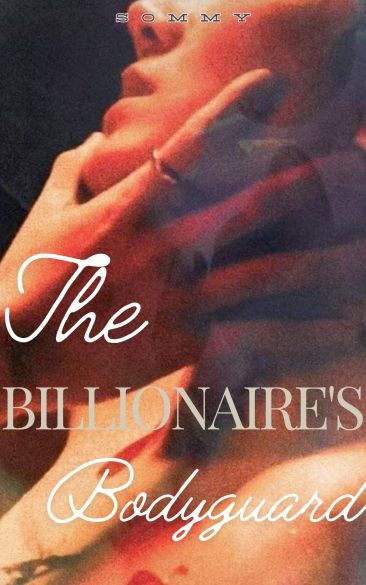






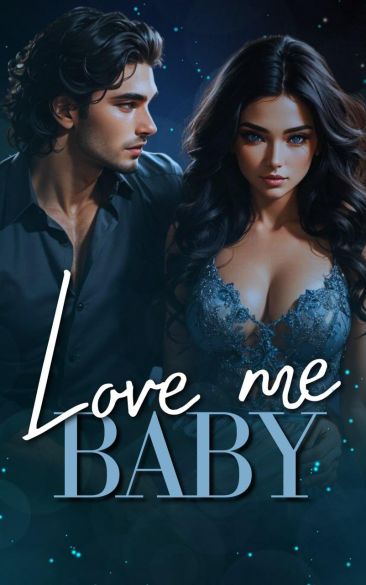
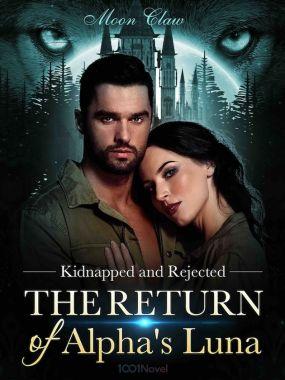




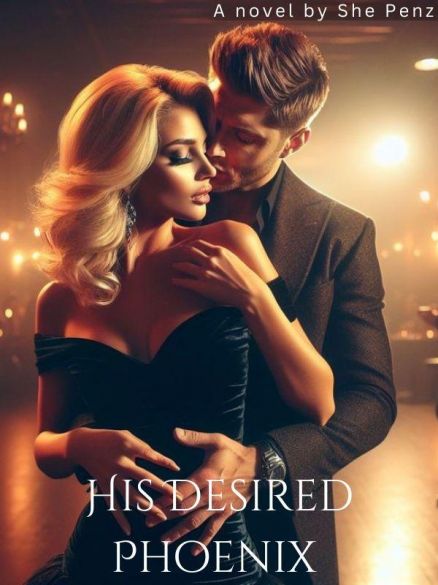





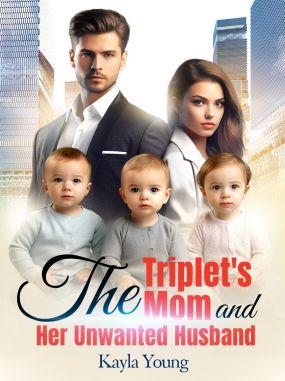





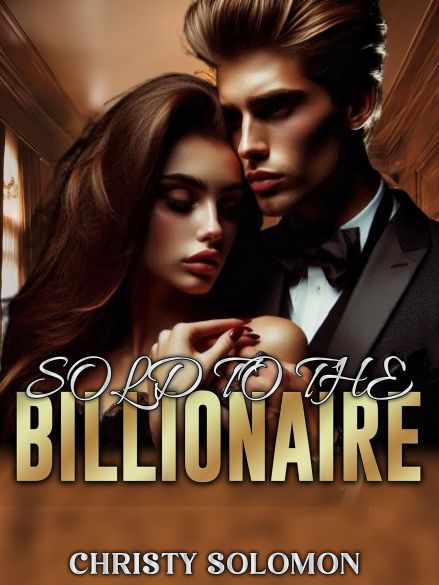
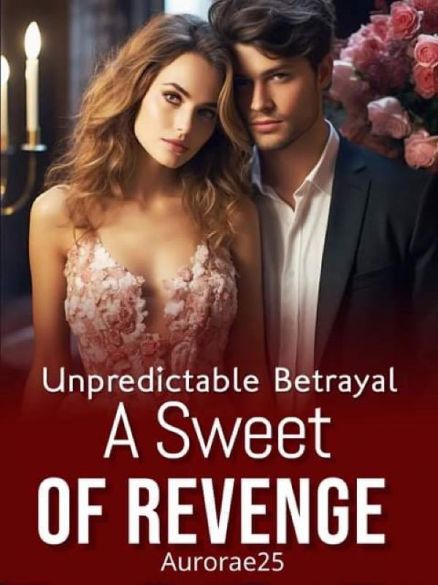

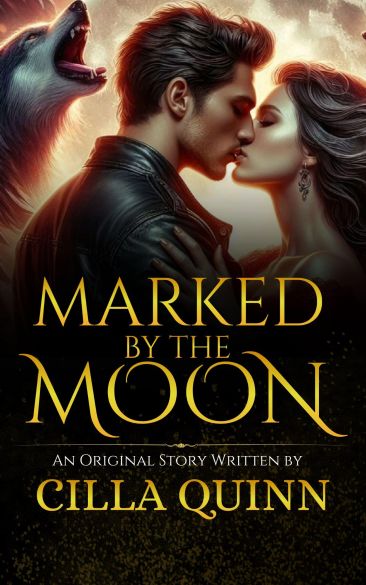


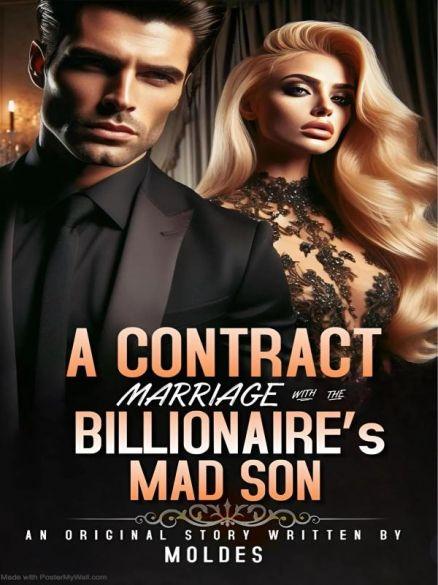


エルドリアの街の灯りが、石畳の道をぼんやりと照らしていた。独立したばかりの記録者(クロニクラー)であるエヴィことエヴェリン・ヘイズは、友人たちとのスリルを求めて、街の片隅に佇む奇妙な店「夜梟の謎(ナイトオウル・エニグマ)」の扉を叩いた。店の主、アリステア・フィンチは、どこか掴みどころのない、ボヘミアンな風貌の男で、客をからかうような軽口を叩きながら、彼らを奥へと案内した。
「今宵お嬢様方が挑戦なさるのは、『古の誓約』をテーマにした最新の部屋でございます。文献によれば、真実の愛を見つけるための儀式だとか…もちろん、ただの遊びですよ、ただのね?」アリステアは意味ありげに片目を瞑った。
エヴィは肩をすくめた。「ええ、もちろん。私たちはただ、ちょっとした非日常を味わいに来ただけだから。」彼女の言葉には、現実主義者らしい冷めた響きがあった。
部屋は薄暗く、古びた巻物や奇妙な装飾品で満たされていた。ゲームは謎解きを進める形で進行し、クライマックスでは、参加者全員で古文書に書かれた文言を唱える「誓約の儀式」が待っていた。エヴィは内心、馬鹿馬鹿しいと思いながらも、友人たちに急かされるまま、よく意味も分からない古語の呪文を口にした。指先で、祭壇に置かれた冷たい石に触れる。それはゲームの小道具のはずだった。
「これで終わり?案外あっけないのね」儀式が終わると、エヴィはそう言って伸びをした。
その夜、自分のアパートメントに戻ったエヴィは、言いようのない違和感に包まれていた。初めは気のせいだと思った。書斎に置いたはずの羽根ペンが床に落ちていたり、誰もいないはずの部屋で不意に冷気を感じたり。
「疲れているのかしら…」
エヴィは独りごち、熱いシャワーを浴びた。だが、浴室から出ると、鏡が奇妙な形で曇っていることに気づいた。まるで、誰かがそこに息を吹きかけたように。
「…まさか」
彼女は眉をひそめ、布で鏡を拭った。その瞬間、背後から誰かにじっと見られているような、肌を刺すような視線を感じた。振り返っても、もちろん誰もいない。
「…やめてよ、気味が悪い」
エヴィは自分に言い聞かせるように呟いたが、心臓は嫌な音を立てていた。
翌日も奇妙な現象は続いた。キッチンでコーヒーを淹れようとすると、戸棚から砂糖壺がひとりでに滑り落ち、床に散らばった。彼女が仕事で使っている幻灯水晶(イメージクリスタル)の焦点が突然合わなくなり、重要な記録が台無しになりかけた。
そして、その夜。エヴィが再びシャワーを浴び終え、湯気で曇った鏡の前に立った時だった。
鏡の表面に、ゆっくりと、しかしはっきりと、水滴が文字を形作り始めた。それはまるで、血のような赤黒い色を帯びていた。
『オレノ……』
エヴィは息を飲んだ。心臓が喉までせり上がってくるようだ。
次の瞬間、さらに文字が続く。
『オレノ……ツマ』
「…妻?」
エヴィはかすれた声で呟いた。全身の血の気が引いていくのを感じた。鏡に映る自分の顔は恐怖に歪んでいた。一体、誰が?何が?
彼女は震える手で鏡に触れようとしたが、その文字はまるで彼女の恐怖を嘲笑うかのように、ゆっくりと滴り落ちて消えていった。だが、その言葉の冷たい感触は、エヴィの魂に深く刻み込まれた。
「冗談じゃないわ…!」
これは、あの密室での「儀式」と関係があるのだろうか?
エヴィの理性的な思考が、得体の知れない恐怖によって揺さぶりをかけられ始めていた。彼女は、自分がとんでもないものに捕らわれてしまったのではないかという、恐ろしい予感に襲われていた。
夜梟の謎での軽はずみな行動が、こんな結果を招くなんて。
エヴィは暗い部屋の中で、ただ一人、見えざる何かの存在を確かに感じながら、震えるしかなかった。
(つづく)