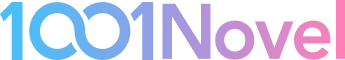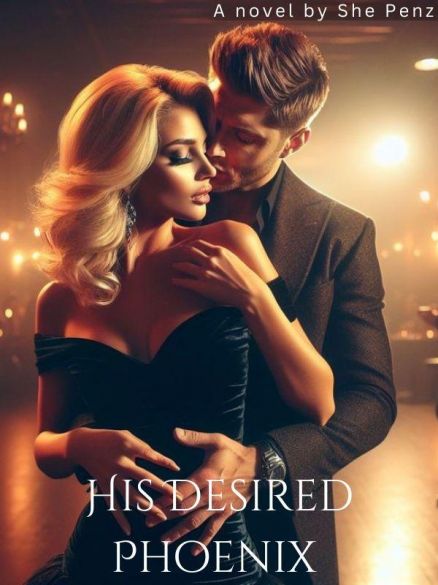




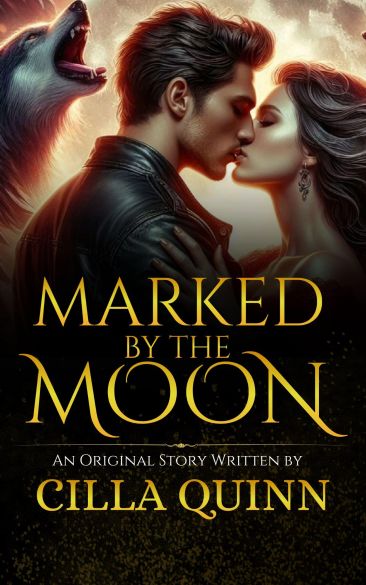

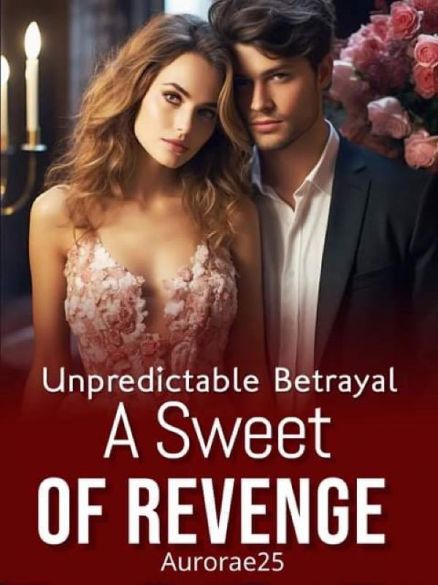
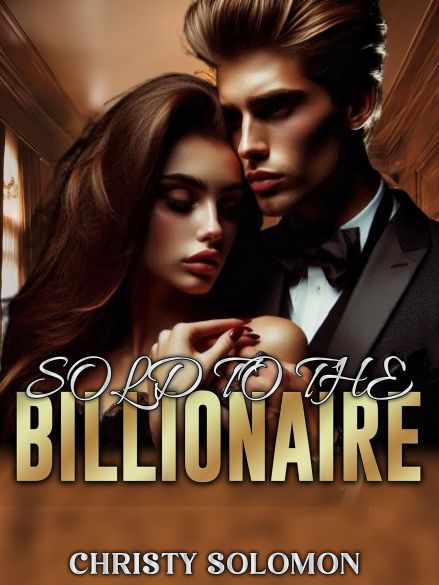


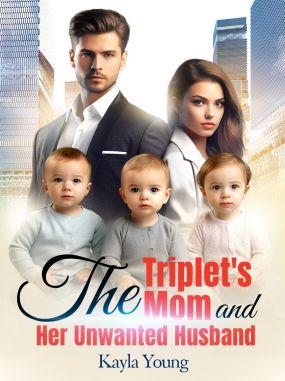



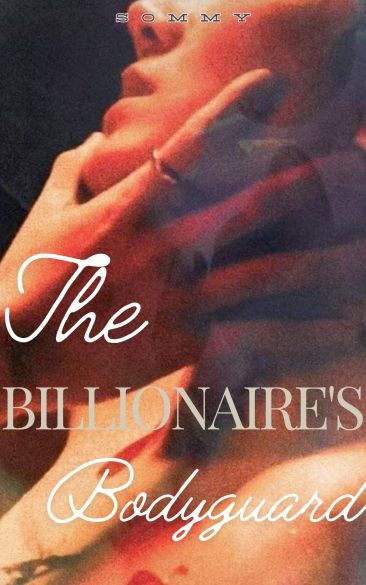


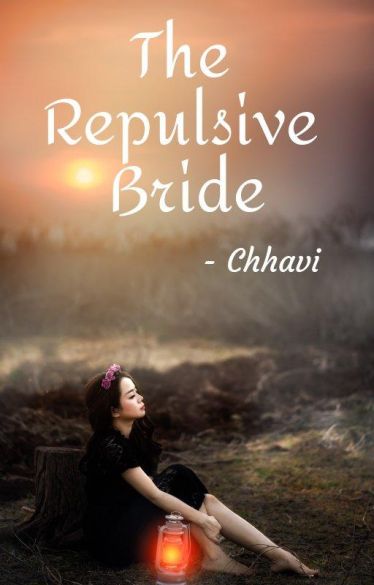


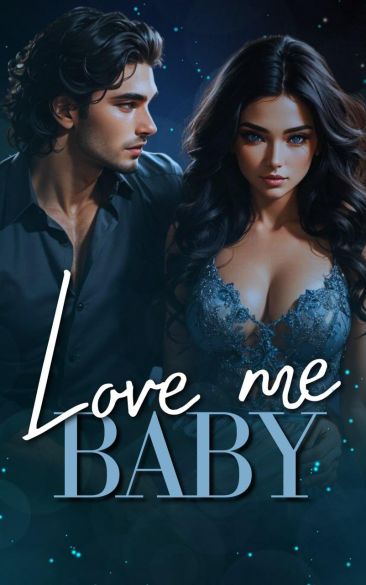








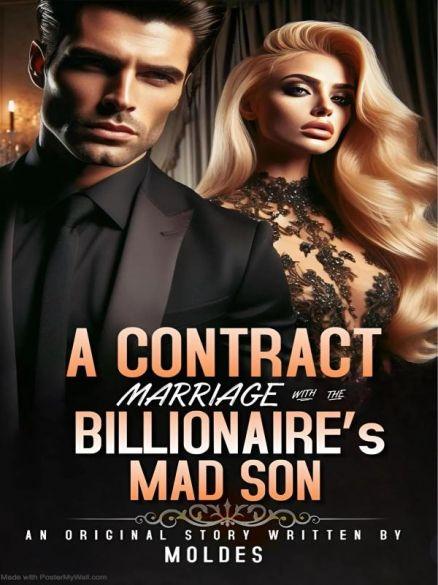

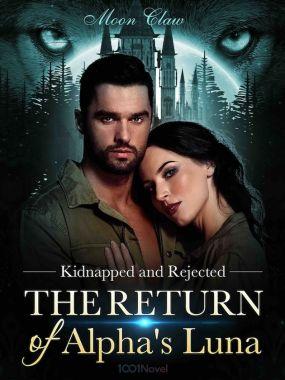
「う……」
頭が割れるように痛い。瞼が鉛のように重く、押し上げようとしても、ぴくりとも動かない。
周囲がやけに騒がしい。女たちの甲高い声、衣擦れの音、そして何か甘ったるい香の匂い。
(どこ…ここ…?)
霞がかかった意識の中で、必死に記憶を辿ろうとする。私は確か、残業続きで疲れ果てて、ようやく帰宅してベッドに倒れ込んだはずだ。なのに、この喧騒は何?
「若様、お目覚めですか?」
すぐ耳元で、若い女の声がした。
その声に促されるように、私はゆっくりと目を開いた。
目に飛び込んできたのは、一面の鮮やかな赤、赤、赤。壁も、垂れ幕も、そして目の前の女が着ている豪奢な着物も。部屋全体が、まるで血で染め上げられたかのような強烈な赤色に包まれていた。
そして、自分の頭にずっしりとした重みを感じる。まるで巨大な石でも乗せられているかのような圧迫感。
「鏡を。鏡を持ってまいれ」
かろうじて絞り出した声は、自分のものではないように掠れていた。
「はい、ただいま」
侍女らしき女――名を花凜(カリン)といったか――が恭しく差し出した白銅の鏡に映ったのは、見慣れた自分の顔ではなかった。
息を呑むほど美しい、けれど冷たく傲慢そうな顔立ちの娘。年は十六、七だろうか。肌は雪のように白く、切れ長の瞳はどこか挑戦的だ。そして何より、その頭には目も眩むような絢爛豪華な文金高島田(ぶんきんたかしまだ)が結い上げられ、重たげな簪(かんざし)がいくつも刺さっている。着ているのは、刺繍が見事な白無垢。
「嘘…でしょ…?」
全身から血の気が引いていくのが分かった。この顔、この状況…まさか。
「若様、何を呆然とされておりますか。今日は祝言の日。上野介(こうずけのすけ)、秋哉(あきや)様がお待ちかねでございますわ」
花凜が、不思議そうな顔で私を見つめる。
アキヤ…?上野介…?
聞いたことのある名だ。いや、正確には「読んだ」ことがある。
私が数日前に、あまりの理不尽な展開に悪態をつきながら読了した、あの古風な恋愛小説――『帝王の業~엇갈린深情~』。その中の、悪役令嬢の名は…。
「…花浅…」
鏡の中の女が、私の声に合わせて唇を動かす。
そうだ、私は花浅。日ノ本王朝の太政大臣、花穆(カボク)の娘。そして、この物語の男主人公である上野介・秋哉に嫁ぎ、女主人公である牧遥(マキハル)を執拗に虐め抜き、最後は一族もろとも破滅する、最悪の悪役令嬢。
「なんで…なんで私が花浅に…!」
パニックで頭が真っ白になる。
これは夢だ。きっと悪い夢を見ているんだ。
「若様、しっかりなさってくださいまし!さあ、お支度の仕上げを」
花凜が慌てたように私の肩を揺する。
その感触が生々しくて、これが夢ではないことを残酷なまでに突きつけてくる。
私は、あの小説の世界に、よりによって最も忌み嫌っていたキャラクターとして転生してしまったのだ。
しかも、今日は秋哉との祝言の日。物語が大きく動き出す、まさにその日だ。
「少し…一人にしてちょうだい」
震える声でそう言うと、花凜は戸惑いながらも部屋を出て行った。
一人きりになった途端、私はへなへなと床に座り込んだ。
重すぎる白無垢と文金高島田が、まるで私をこの世界に縛り付ける鎖のように感じられる。
(どうしよう…どうすればいいの…?)
記憶が洪水のように蘇る。
花浅の傲慢な振る舞い。秋哉への異常な執着。牧遥への陰湿な嫌がらせの数々。そして、その果てに待つ、無惨な末路。
首を吊るか、毒を飲むか、あるいは打ち首か…確か、そんな凄惨な死に方だったはずだ。
「嫌よ…そんなの絶対に嫌!」
現代日本の平凡な会社員だった私が、なぜこんな目に遭わなければならないの?
小説を読んでいる時は、「ざまぁみろ!」なんて思っていたけれど、いざ自分がその立場になってみると、恐怖でしかない。
(そうだ、湯浴みをしよう…少しでも冷静にならないと…)
花浅の記憶を頼りに、部屋の奥にある湯殿へ向かう。
贅沢な檜の湯船には、なみなみと湯が張られていた。
重い衣装を脱ぎ捨て、冷たいと感じるほどの湯に身を沈めると、ようやく少しだけ思考がクリアになる気がした。
「まず、状況を整理しなきゃ」
自分に言い聞かせる。
私は花浅。今日は秋哉との結婚式。
この結婚は、花浅の父親である花穆が、権力をさらに強固にするために仕組んだ政略結婚だ。
秋哉は、表向きは花浅を「幼い頃の命の恩人」と誤解しているため、この結婚を受け入れている(本当の恩人は牧遥なのに!)。しかし、内心では花浅のことを疎んじている。そして、近いうちに牧遥と運命的な出会いを果たし、彼女に心惹かれていく。
そこから、花浅の嫉妬と暴走が始まるのだ。
「…牧遥…」
あの小説のヒロイン。彼女の一家は、確か数日後、無実の罪で処刑されるはずだ。それが、秋哉と牧遥の悲恋を加速させる大きな要因となる。
(待って…数日後って…もう時間がないじゃない!)
湯の中にいるのも忘れて、思わず立ち上がりそうになる。
もし、牧遥の一家の処刑を止められなかったら?
物語は原作通りに進んでしまう。そして私も、破滅へと一直線だ。
「そんなの、絶対に阻止しないと!」
強い生存本能が、心の奥底から湧き上がってきた。
死にたくない。こんな理不尽な運命、受け入れてたまるものか。
原作知識がある。それが唯一の武器だ。
この理不尽な運命、絶対に私が変えてみせる!
だが、どうやって?
今夜は、あの冷酷で、花浅を蛇蝎の如く嫌っている秋哉との初夜なのだ。
悪役令嬢としての最初の「試練」が、もう目前に迫っている。
湯船の中で、私は固く拳を握りしめた。
その震えは、恐怖か、それとも武者震いか。自分でも分からなかった。