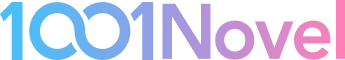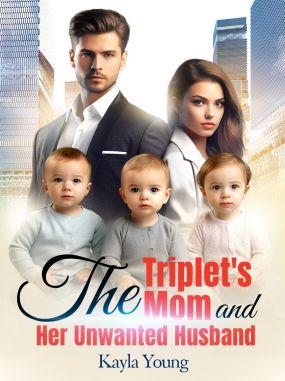
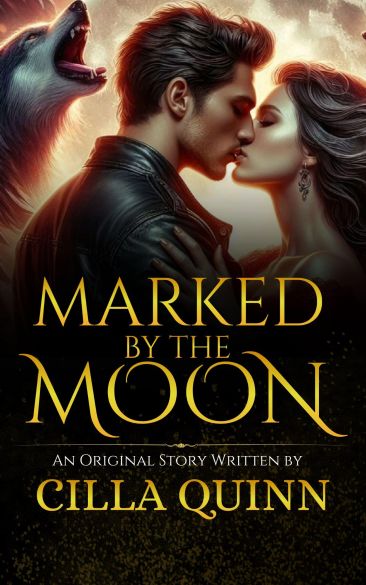









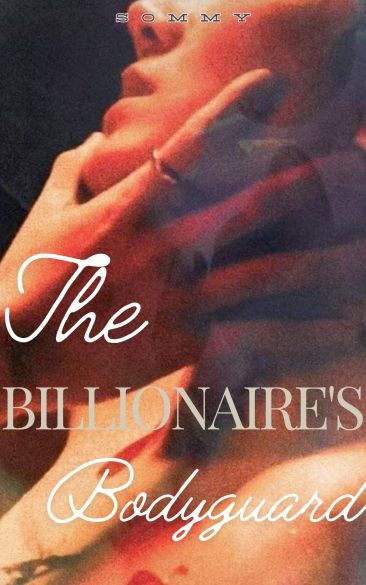
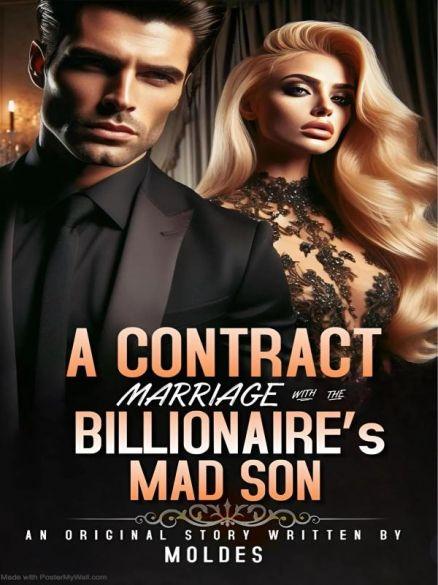

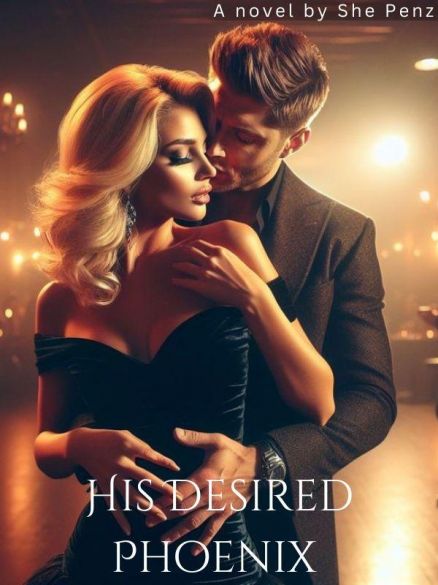



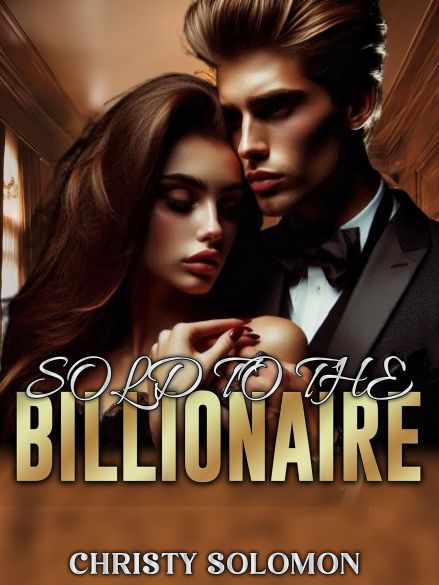




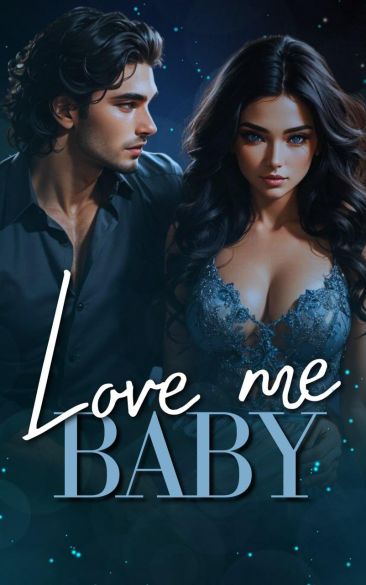
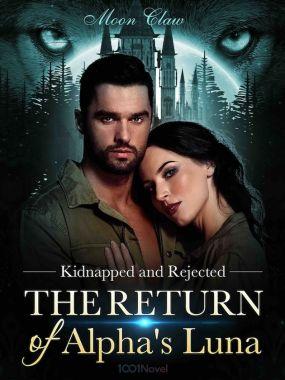








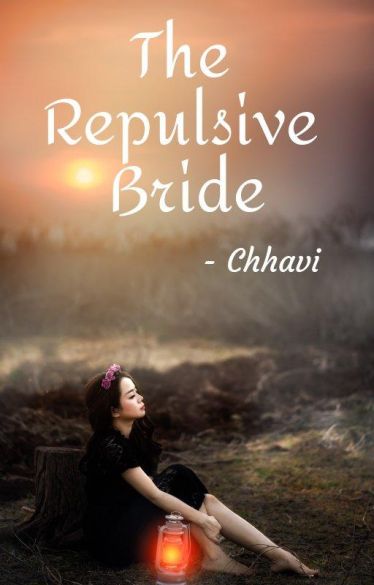

「えー、今日から我がクラスでは、通称『成績向上ペア制度』を実施する!」
朝のホームルーム。担任の山田先生が、教壇の上で高らかに宣言した。通称、って自分で言っちゃうあたり、もうネーミングセンスのなさを露呈している。
「目的は、成績上位者が下位者を引っ張り上げ、クラス全体の学力向上を目指す!よって、席替えもこれに基づいて行う!」
教室が一瞬、ざわついた。
私、浅川静香。このエリート進学校において、貴重な「成績下位層」をがっちりキープしている、ある意味エリートだ。親のコネと、あとはまあ、若干の寄付金でこの学校にもぐりこんだ私は、勉強なんて二の次、三の次。人生楽しんだもん勝ち、がモットーだ。
「ペアの組み合わせは…」
山田が面倒くさそうに名簿に目を落とそうとした時、私はパッと手を挙げた。
「先生!私、選びたい人がいます!」
「ほう、浅川がか?珍しいな。誰だ?」
ニヤニヤする山田。どうせ私がまた何か面白いことをやらかすと思っているのだろう。
「私、北川颯馬くんとペアになりたいです!」
シン、と教室が静まり返った。
無理もない。北川颯馬。彼は、この学校でもトップクラスの秀才。入学以来、学年首席の座を誰にも譲ったことのない、伝説の男。ただし、その存在感は極めて希薄。いつも教室の隅で静かに本を読んでいるか、窓の外を眺めているかで、彼が声を発するのを聞いた者はほとんどいない。おまけに、家が貧しいらしく、制服はヨレヨレ、髪も伸び放題。見るからに陰気な「ガリ勉」タイプ。
「はあ?静香、お前、本気かよ?」
隣の席の須藤司が、信じられないという顔で私を見た。須藤は、そこそこの金持ちの息子で、ルックスも悪くない。私のことを気に入っているらしく、何かとちょっかいを出してくるが、正直うざいだけだ。
「もちろん本気だよ?私、頭いい人が好きなの」
私がニコリと笑うと、須藤はさらに顔をしかめた。
「やめとけよ、静香。北川なんて…あいつ、たぶん『特待生』だぜ?俺たちとは住む世界が違うんだよ。俺がバッチリ教えてやるからさ」
須藤が勝ち誇ったように言った。
『特待生』。
私たちの通うこの私立明青学園は、県内でも有数の進学校であり、同時に授業料も高額だ。しかし、ごく稀に、学費免除で入学できる『特待生』の枠が存在する。北川颯馬は、その数少ない特待生の一人ではないかと噂されていた。彼の生活ぶりや、どこか影のある雰囲気が、その噂に拍車をかけていた。
その言葉を聞いた瞬間、それまで教科書に目を落としていた北川颯馬の肩が、ピクリと震えたのを私は見逃さなかった。彼の頭が、さらに深く垂れられた気がした。
(特待生…だから何だって言うのよ!)
私は心の中で須藤に悪態をついた。むしろ、そんなハンデをものともせず、トップの成績を維持している彼を、私は素直に尊敬していた。それに、何より面白そうじゃないか。
「先生、いいですよね?北川くんと私で」
私が念を押すと、山田は面白がるように頷いた。
「まあ、浅川がそこまで言うならな。北川、いいか?」
颯馬は、顔を上げないまま、小さく、本当に小さく頷いた。
こうして、私と彼の、奇妙な同級生以上、友達未満の関係が始まった。
新しい席は、窓際の一番後ろ。隣の席になった颯馬は、想像以上に寡黙だった。私が一方的に話しかけても、「…ああ」とか「…うん」とか、単語でしか返ってこない。しかも、その声が小さすぎて聞き取れないこともしばしば。
初日から、私はマシンガンのように喋り続けた。
「ねえ、北川くんってさ、いつも何の本読んでるの?難しそうなやつだよねー」
「……」
「私、数学とか全然わかんなくてさ。特に二次関数?あれ発明した人、ちょっとどうかと思うんだよねー」
「……」
さすがの私も、だんだん心が折れそうになってきた。壁と話している方がまだマシかもしれない。
業を煮やした私が、ついにため息をついた瞬間だった。
「浅川さん」
初めて、彼の方から私に声がかかった。びっくりして彼の方を見ると、彼は相変わらず俯き加減だったけれど、その黒曜石のような瞳が、チラリと私を捉えた。
「…ちゃんと、問題、解いてる?」
「え?あ、うん、まあ…」
しどろもどろになる私に、彼は少しだけ強い口調で言った。
「明日からは、ちゃんと真面目に問題に取り組んでくれる?そうしないと、ペアの意味がない」
彼の言葉は正論だった。でも、そのあまりにストレートな物言いに、私は少しカチンときた。
(なによ、この朴念仁!ちょっとは愛想良くしたってバチは当たらないでしょうが!)
「わ、わかってるわよ!私だって、少しは成績上げたいって思ってるんだから!」
私はむきになって言い返した。
その日の放課後。私は早速、数学の問題集と格闘していた。案の定、開始五分で頭が沸騰しそうになる。
「うーん…ここ、どういうこと…?」
チラリと隣の颯馬を見る。彼は黙々と、何かの数式をノートに書き連ねている。その集中力は凄まじく、私が隣でうんうん唸っていても、全く気にする素振りもない。
(ああもう、こうなったら!)
私は意を決して、彼の袖をツンツンとつついた。
「ねえ、北川くん…ちょっとだけ、ここ教えてくれないかな…?」
彼は一瞬、迷惑そうな顔をした。が、すぐに諦めたようにペンを置き、私のノートを覗き込んだ。そして、信じられないほど分かりやすく、丁寧に、その問題を解説してくれたのだ。
彼の声は相変わらず小さかったけれど、その説明は魔法のように私の頭に入ってきた。
「…わかった?」
「うん!すごい!北川くん、天才!」
私が素直に賞賛すると、彼の耳がほんの少しだけ赤くなったように見えた。
(あれ?もしかして、照れてる?)
その小さな変化に、私はなんだか嬉しくなってしまった。
この朴念仁にも、可愛いところがあるじゃないか。
そして私は、この日から、彼への「先行投資」を開始することを心に決めた。
まずは、彼のその痩せっぽちの体を何とかしなければ。
そのためには、まず胃袋から掴むのが定石よね?
そう、この時の私はまだ、この「先行投資」が、とんでもない「見返り」を生むことになるなんて、夢にも思っていなかったのだ。
そして、彼が抱える孤独の深さも、彼の瞳の奥に隠された熱い想いも、まだ何も知らなかった。
ただ、この風変わりな天才との学校生活が、少しだけ面白くなりそうな予感がしていただけだった。