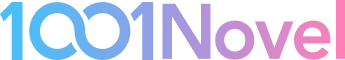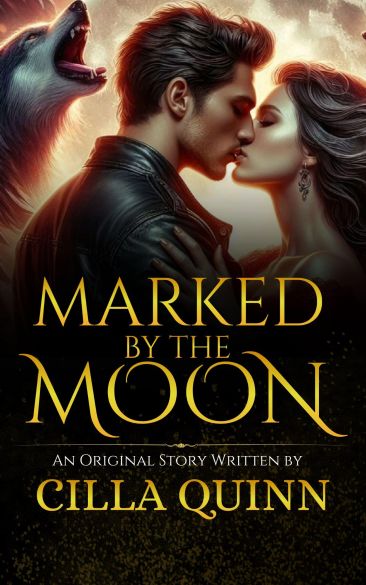




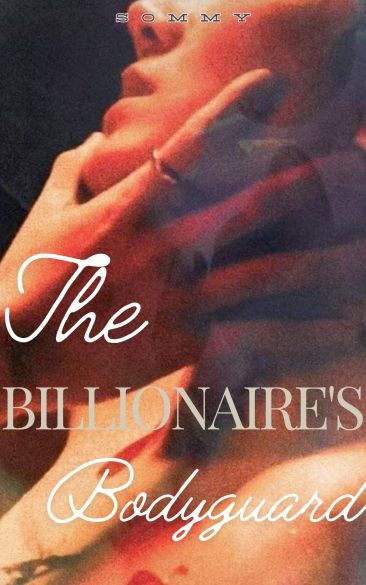


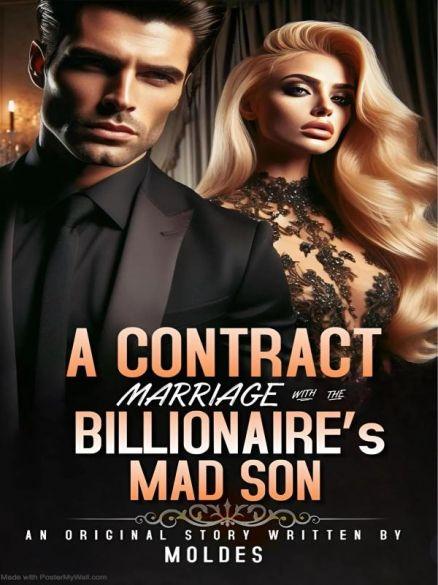





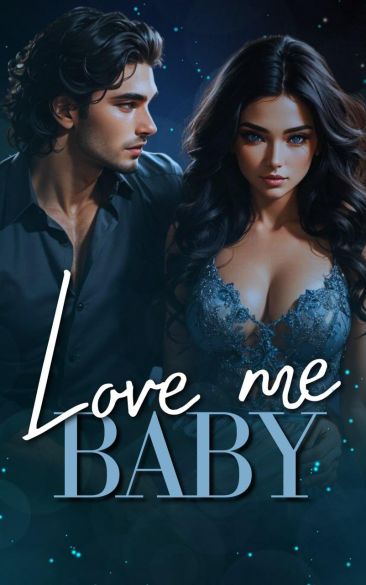







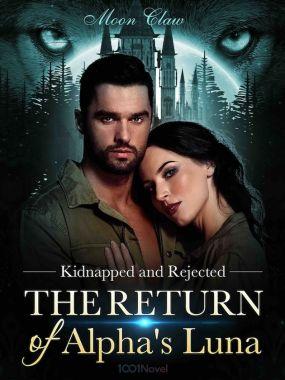
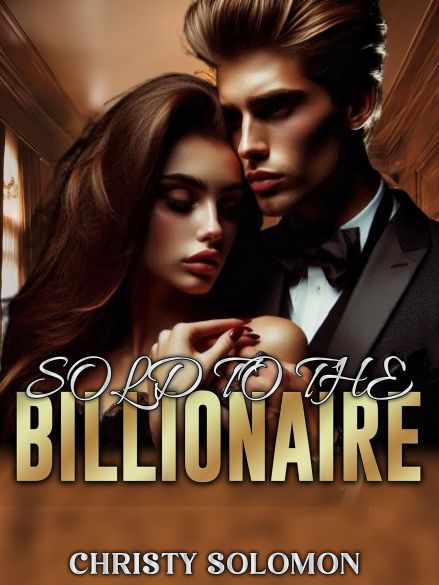


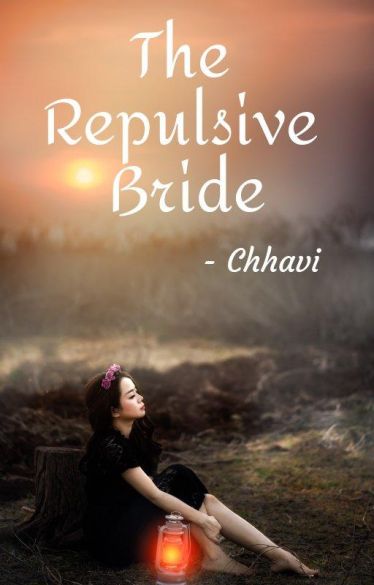


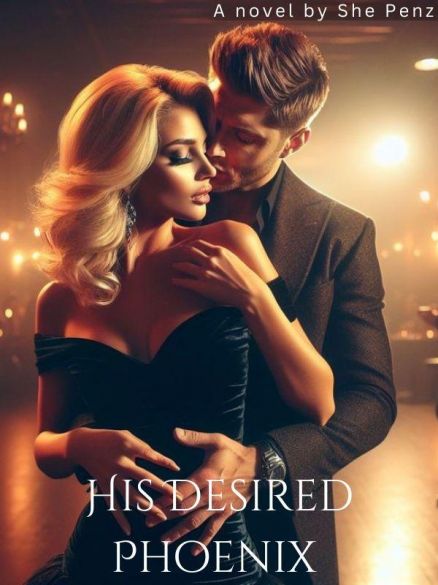
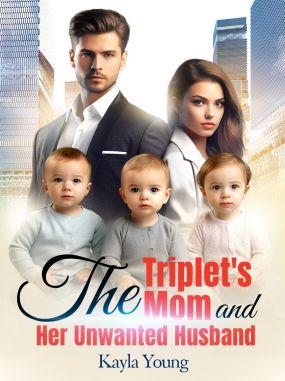
けたたましいサイレンの音が遠のき、高級VIP病棟の静寂が戻ってきた。
藤原獅苑(ふじわら しおん)は、ゆっくりと瞼を開いた。真っ白な天井が目に映る。頭には鈍い痛み。
「…ここは?」
掠れた声で呟くと、傍に控えていた執事の江川(えがわ)が素早く反応した。
「獅苑様!お目覚めですか!よかった…」
江川の顔には安堵の色が浮かんでいる。
獅苑はゆっくりと身を起こそうとした。
「詩織(しおり)は?湊詩織はどこだ?」
その言葉に、江川の顔が凍りついた。
周囲にいた医師や看護師たちも、困惑した表情で顔を見合わせる。
「獅苑様…湊様は…」
江川が言い淀む。
「詩織を呼べ。今すぐにだ」
獅苑の声は、普段の冷徹さとは裏腹に、どこか幼い子供のような焦燥感を帯びていた。まるで、大切な人形を取り上げられた子供のように。
「それが…」
「何だ?詩織は俺のそばにいるはずだろう?」
獅苑は眉を顰め、記憶を探るようにこめかみを押さえた。彼の記憶は、詩織を腕の中に抱きしめ、彼女の温もりを感じていたところで途切れている。あの甘く、満たされた日々。
「獅苑様、事故に遭われたのです。記憶が少々混乱されているのかもしれません」
医師が慎重に言葉を選ぶ。
「事故?ああ、そうか…」獅苑は頷いた。「それで、詩織は?怪我はないのか?早く顔を見せろと伝えろ」
彼の頭の中では、詩織はまだ自分の庇護下にあり、常に自分のそばにいる存在だった。
「…獅苑様、湊様は、もう藤原家には…」
江川が意を決して口を開いたが、獅苑の鋭い視線に遮られた。
「何を言っている?詩織が俺から離れるわけがないだろう」
獅苑は苛立ちを隠さず、ベッドサイドの電話に手を伸ばした。
「自分で連絡する」
しかし、登録されているはずの「詩織」の番号に何度かけても、呼び出し音が鳴る前に「お客様の都合によりお繋ぎできません」という無機質なアナウンスが流れるだけだった。
メッセージアプリも開いてみる。最後に送った「おはよう、詩織」というメッセージは、既読にすらなっていない。ブロックされている。
「…どういうことだ?」
獅苑の顔から血の気が引いた。
ありえない。詩織が俺を拒絶するなんて。
あの、いつも俺だけを見つめ、俺の腕の中で安心しきった顔で眠る詩織が?
その時だった。
ゴロゴロゴロ…
窓の外から、不穏な低い音が響いてきた。空が急速に暗くなっていく。
稲光が走り、数秒遅れて、腹に響くような轟音が病室を揺るがした。
ザーッという音と共に、大粒の雨が窓ガラスを叩き始める。
獅苑の身体が、ぴくりと震えた。
「…雨…?」
彼の瞳が、急速に焦点を失っていく。
「あ…ああ…」
浅い呼吸が繰り返され、その目は獣のように赤く充血し始めた。
「まずい!」江川が叫んだ。「獅苑様の…発作が!」
医師たちが慌てて鎮静剤を準備しようとするが、獅苑はそれを振り払った。
「詩織…詩織はどこだ!詩織を呼べ!」
彼の声はもはや懇願ではなく、獣の咆哮に近い。
記憶は最も詩織を寵愛していた頃に戻っているが、身体は雨に対するトラウマを克明に覚えていた。
「詩織がいないと…俺は…!」
獅苑は頭を抱え、ベッドの上でのたうち回る。
その姿は、日本経済を影で動かすと言われる藤原コンツェルンの若き総帥のそれとは到底思えない、痛々しく、そして恐ろしいものだった。
「くそっ!」江川は舌打ちし、ポケットからスマートフォンを取り出した。「何としてでも湊詩織を見つけ出せ!今すぐにだ!彼女がいなければ、獅苑様が…!」
江川の額には脂汗が滲んでいた。
このままでは、獅苑は自分自身をも破壊しかねない。
あの雨夜の惨劇が、再び繰り返されるかもしれないのだ。
「詩織…どこだ…詩織ぃぃぃぃっ!」
獅苑の絶叫が、雷鳴と共に病室に響き渡った。
その声は、愛しい者を求める悲痛な叫びであり、同時に、破滅へと向かう獣の呻きでもあった。
藤原獅苑の失われた記憶。そして、雨が呼び起こす狂気。
その唯一の鍵を握る女、湊詩織は、今どこにいるのか?
そして、彼女は戻ってくるのだろうか?
嵐の夜は、まだ始まったばかりだった。