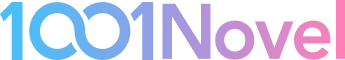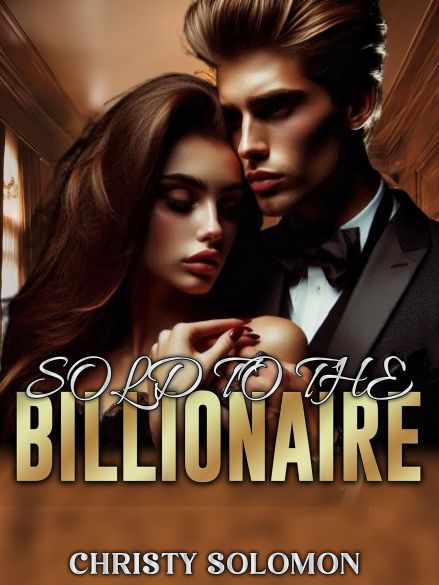

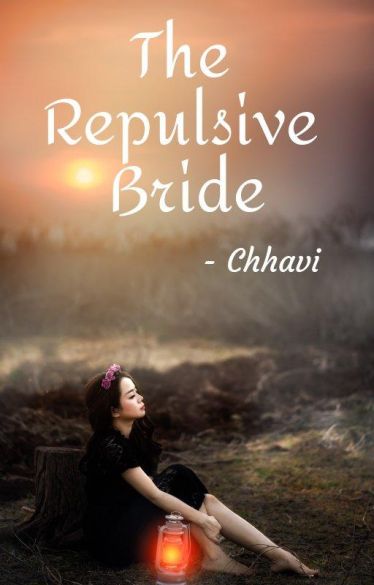
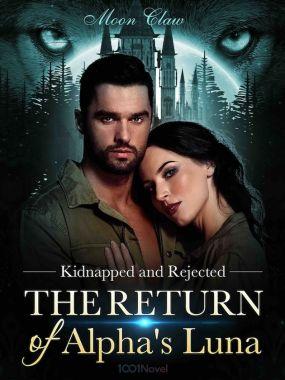




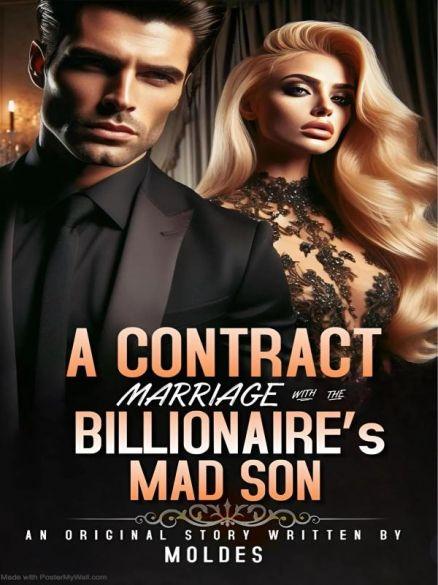






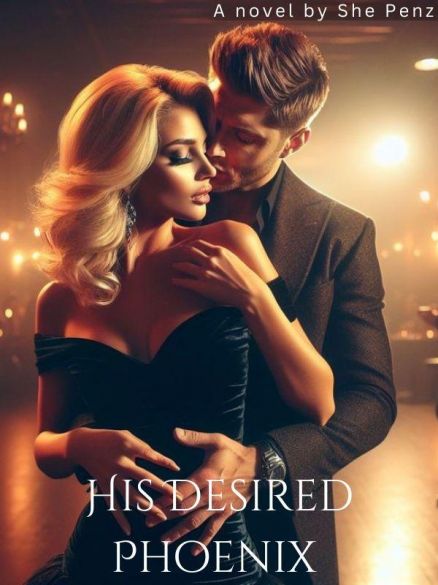
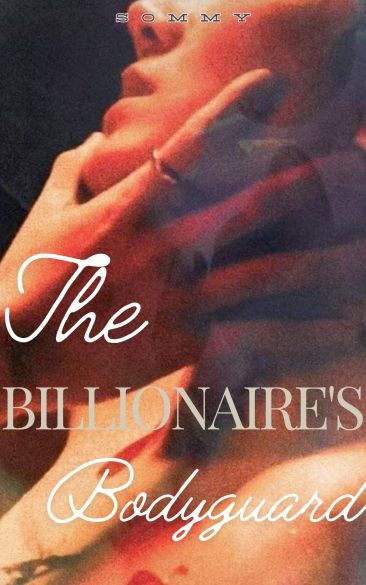




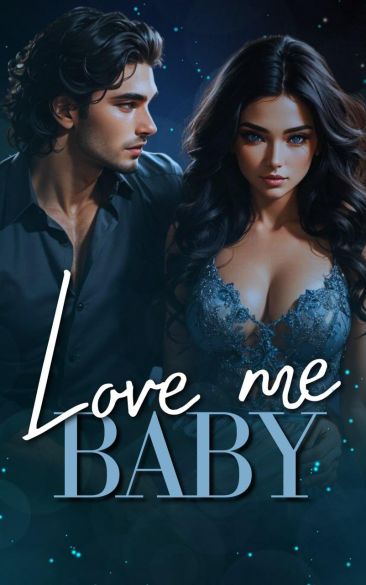
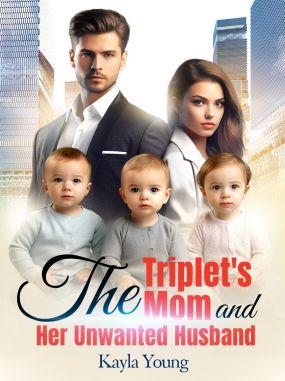

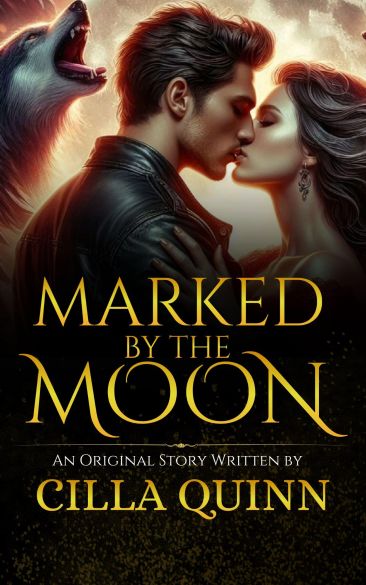
「結婚はできません」
冷え冷えとした応接室。父の怒りに満ちた目が、私、京極清葉(きょうごく きよは)を射抜く。
京都の名家、京極家の長女として、私は望まぬ政略結婚を強いられていた。相手は神戸の高遠(たかとお)グループの御曹司。会ったこともない男。
「これは決定事項だ。お前個人の感情で覆るものではない」
「では、私に子供ができたら? それでも結婚を強いますか?」
父の眉がピクリと動いた。
そう、これが私の最後の切り札。
妊娠してしまえば、名家同士の縁談など破談になるに違いない。
私は家を飛び出し、計画を実行に移した。
身分を隠し、「清(きよ)」と名乗り、都会の片隅で貧乏学生を装った。
ターゲットは、同じ大学の先輩、凛(りん)さん。家柄も資産もない、けれどどこか影のある美しい人。彼なら、後腐れなく別れられるはず。
計算通り、私たちは恋人同士になった。
そして、彼の子供を身ごもった。
計画は完璧だった。
私は彼に置き手紙と「慰料」として貯金の五十万円を残し、姿を消した。
これで自由になれる。そう、思ったのに。
数週間後、父に呼び戻された実家で、私は衝撃の事実を突きつけられる。
「高遠家の凛様がお前と話がしたいそうだ。わざわざ京都までお越しくださった」
高遠…凛? まさか。
重い足取りで向かった客間で待っていたのは、あの日別れたはずの男、凛さんだった。
けれど、いつもの洗いざらしのシャツではなく、上質なスーツに身を包み、冷徹な空気を漂わせている。
彼は私の膨らみ始めたお腹に鋭い視線を向けると、歪んだ笑みを浮かべた。
「五十万円か。俺の胤(たね)を買うには、随分と安いもんだな、俺の…愛しい婚約者さんよ」
彼の口から紡がれた「婚約者」という言葉。
まさか、彼が、あの高遠グループの御曹司、高遠 凛(たかとお りん)だったなんて。
私の計画は、最初から彼の手のひらの上だったのだろうか。
絶望と、微かな恐怖が、私を包み込んだ。