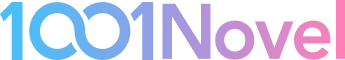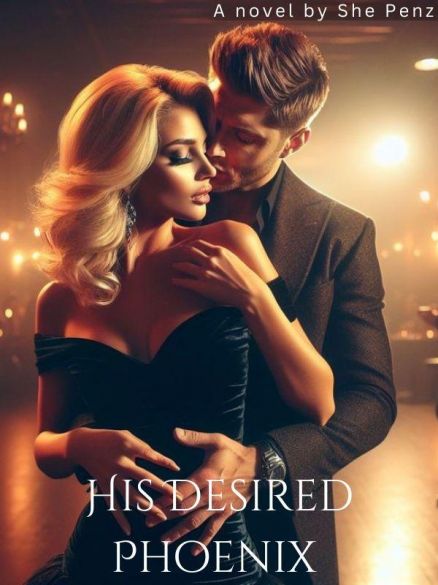

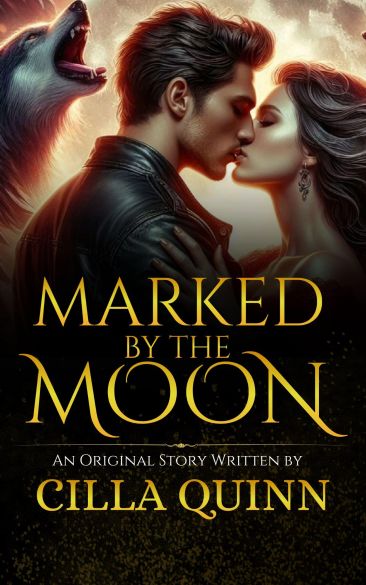

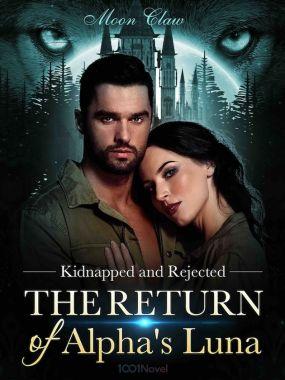




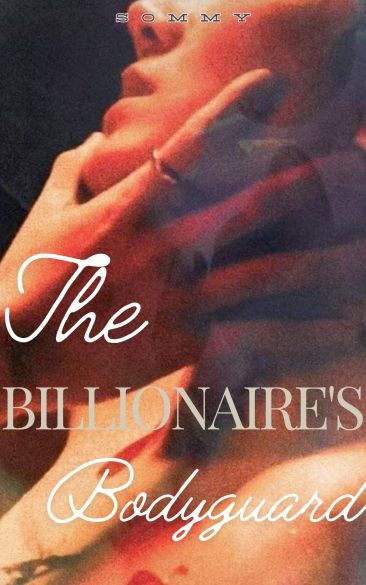






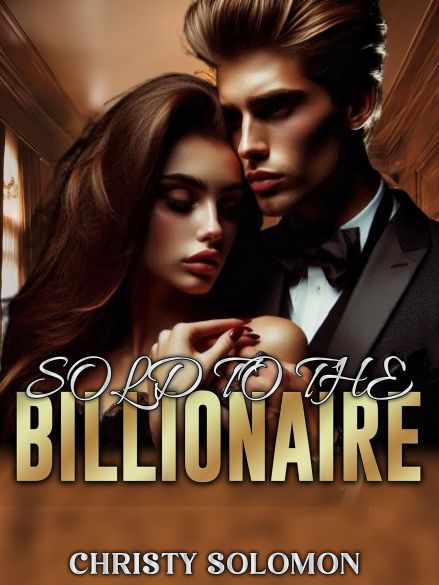

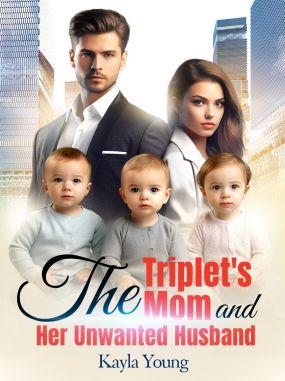











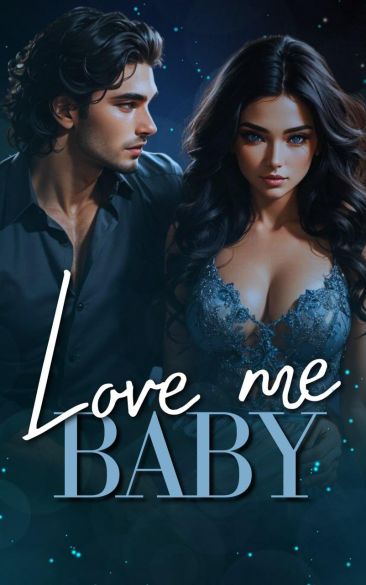
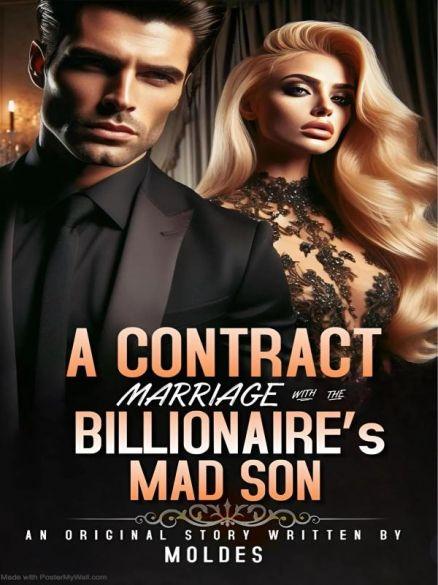


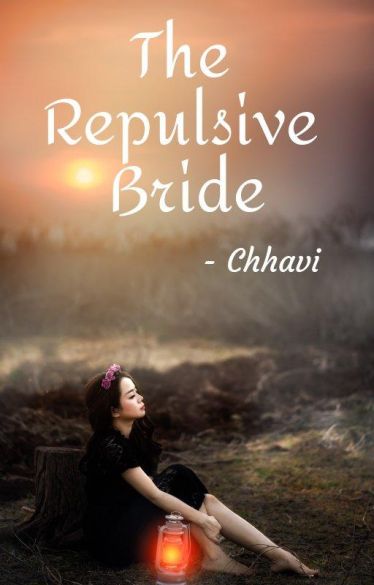
若宮淳(わかみや じゅん)は、午前三時の着信音で叩き起こされた。ディスプレイには「相良清隆(さがら きよたか)」の名前が冷たく光っている。
「はい」
掠れた声で応答すると、電話の向こうから低く、感情の読めない声が響いた。
「月影(つきかげ)に来い。例の企画書だ」
月影。六本木の夜に煌めく、会員制の高級クラブ。相良清隆が懇意にしている店だった。
「…今すぐ、ですか?」
「ああ。十分で来い」
一方的に切れた通話に、淳は深いため息をついた。ベッドから這い出し、クローゼットから地味なスーツを取り出す。もう何年も、彼の深夜の呼び出しには慣れていた。
タクシーを飛ばし、月影に着いたのは十五分後だった。息を切らしてエントランスを抜け、彼の指定した個室へ向かう。磨き上げられた重厚な扉の前。ノックしようとした手が、ふと止まった。
親指一本分ほどの隙間から、聞き慣れた声と、知らない男の声が漏れ聞こえてきたのだ。
「で、相良。若宮のこと、どうするつもりだ?秘書にしては可愛がりすぎじゃないか?」
それは清隆の友人、確か桜井(さくらい)という男の声だった。
淳は息を飲んだ。心臓が嫌な音を立て始める。
やがて、清隆の静かな声が響いた。
「遊びだ。本気にするな」
一瞬の沈黙。そして、決定的な一言。
「それに、相良の本家が、あんな女を許すと思うか?たかが秘書だ。せいぜい、愛人どまりだろう」
淳の手が震え、持っていた企画書の封筒が床に落ちそうになるのを、必死で堪えた。
呼吸が止まる。頭が真っ白になった。
遊び…愛人どまり…
その言葉が、ナイフのように淳の胸を突き刺した。
これ以上、聞いてはいられなかった。
淳は踵を返し、近くにいたウェイターに企画書を押し付けるように渡した。
「相良社長に、と」
それだけ言うと、逃げるように月影を飛び出した。外は、いつの間にか土砂降りの雨になっていた。傘なんて持っていない。冷たい雨が、淳の頬を叩き、涙なのか雨なのか、もうわからなかった。
空っぽのタクシーを捕まえ、自宅マンションへ向かう。雨音が、まるで淳の世界を全て飲み込んでしまおうとしているかのように、激しく窓を叩いた。
彼、相良清隆と出会ったのは、大学の入学式。新入生代表として挨拶する彼の姿は眩しく、淳は一瞬で恋に落ちた。それから四年間、遠くから彼を見つめるだけの日々。卒業後、奇跡的に相良グループの社長秘書として採用され、夢が半分叶ったような気がした。
そして、さらに二年後。彼の指が初めて彼女の肌に触れた夜。それから四年、彼と社長と秘書、そして夜は恋人という歪な関係が続いていた。
八年間。私の八年間は、彼にとって「遊び」でしかなかったのか。
びしょ濡れのまま部屋に入ると、タイミング悪く携帯が鳴った。実家の父からだった。
「淳か?例のお見合いの話、どうなった?お前ももう、いい歳なんだぞ」
「……」
「明日までには返事をすると言っただろう。相手方も待っておられるんだ」
父の心配する声に、淳はかろうじて答えた。
「…うん。明日…明日には、必ず返事するから」
電話を切り、淳はソファに崩れ落ちた。結婚。そんなもの、清隆以外考えたこともなかった。
どれくらいそうしていただろうか。玄関のドアが開く音で、淳は我に返った。清隆が帰ってきたのだ。いつも彼が使う合鍵の音。
彼はリビングに入ってくると、びしょ濡れの淳を見て眉をひそめた。
「どうした、その格好は」
「…雨に降られて」
「そうか」
彼はそれ以上何も言わず、ネクタイを緩めながら淳に近づいた。そして、濡れた髪を無造作にかき分け、唇を重ねてくる。
淳の体は、彼の愛撫に慣らされていた。だが今夜は、人形のようにされるがままだった。彼の熱が伝わってくる。けれど、淳の心は凍りついたままだった。
寝室に運ばれ、乱暴に服を剥ぎ取られる。彼の重みがのしかかり、いつものように求められる。
彼の荒い息遣いと、自分の心の空虚さの対比が、淳をさらに絶望させた。
行為が終わった後、清隆はすぐに淳に背を向けた。いつものことだ。
暗闇の中、淳は震える声で、最後の望みを託して尋ねた。
「清隆さん…」
「なんだ」不機嫌そうな声。
「あの…父が、結婚を急かすの」
「……」
「私も、もう…そういう年齢だし…もし、清隆さんに少しでもその気があるなら…」
そこまで言って、淳は言葉を切った。怖くて、彼の顔が見られない。
しばらくの沈黙の後、清隆はゆっくりと振り返った。暗闇に慣れた目が、彼の冷たい表情を捉える。
「そうか。いいんじゃないか」
彼の声には何の感情もこもっていなかった。
「お前の人生だ。よく考えろ」
淳の心臓が、ギリギリと音を立てて軋んだ。
「なんなら、俺がお前の相手を見定めてやってもいい」
その言葉が、とどめだった。
ああ、そうか。本当に、ただの遊びだったんだ。
彼の目に映る自分は、都合のいい女でしかなかった。結婚なんて、万に一つも考えていなかったのだ。
涙が、とめどなく溢れてきた。だが、声は出なかった。
清隆はそれに気づく様子もなく、再び淳に背を向け、やがて寝息を立て始めた。
淳は、暗闇の中で静かに泣き続けた。
八年間の恋が、終わった。いや、終わらせなければ。
翌朝、清隆がまだ眠っている間に、淳は身支度を整えた。
そして、リビングのパソコンに向かい、一文字一文字、力を込めてタイプした。
「辞職願」と。
まだ微かに雨の匂いが残る窓の外を、淳は虚ろな目で見つめていた。
これから、どうすればいいのだろう。
いや、まずはこの関係を終わらせる。それからだ。
ふと、昨夜の父の言葉を思い出す。「明日までには返事を」。
その「明日」が、もう来てしまっている。
淳は、重い決意を胸に、印刷されたばかりの辞職願を、そっとハンドバッグにしまった。
清隆の会社へ向かう足取りは、まるで鉛を引きずっているかのようだった。